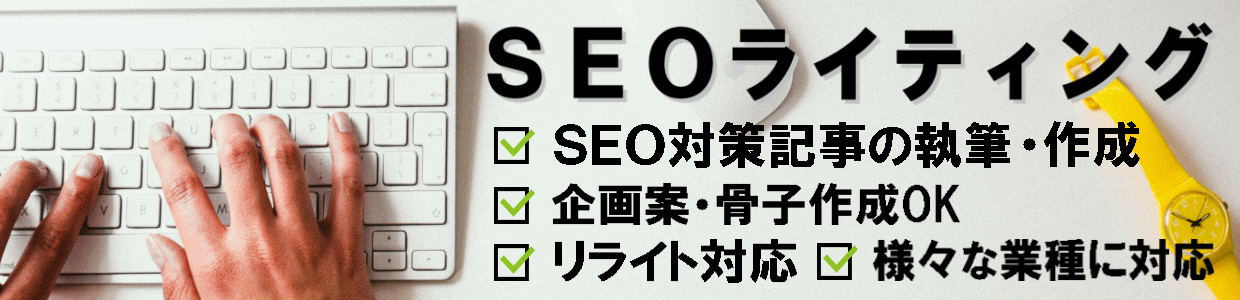Webライティングの書き方とは?SEO Webライターが解説!コンテンツ ライティングの基本
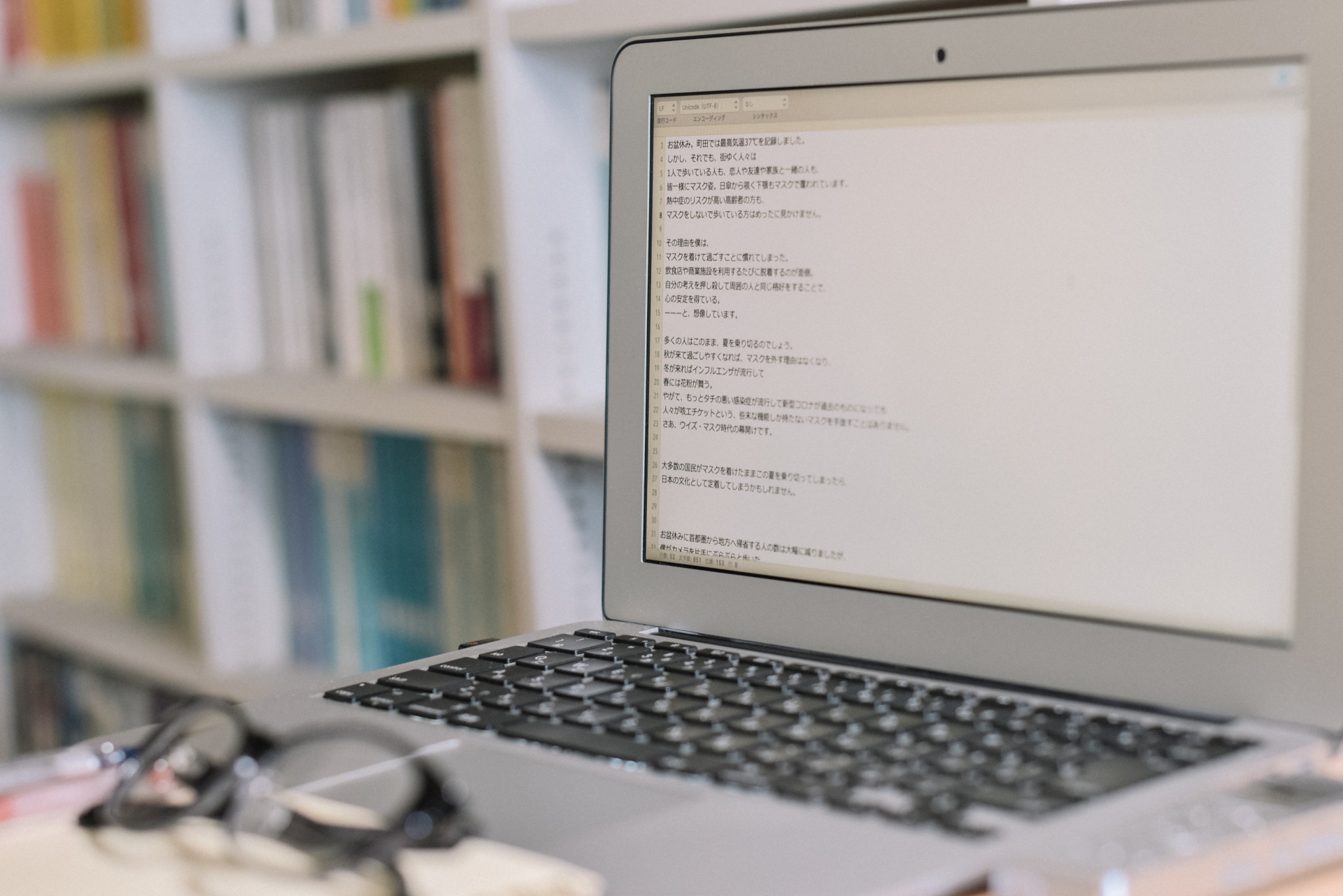
インターネットの普及とともに、自社でオウンドメディアを所有する企業も増えてきました。オウンドメディアを運営するために必要不可欠なのが「コンテンツ」です。
コンテンツの中でも検索エンジン上位表示を達成するために必要なのが「記事」です。そしてこの記事を作成するために重要なテクニックが「Webライティング」です。
当記事ではWebライティングについての書き方やルール、コンテンツライティングの基本などについて解説します。
Webライティングとは
Webライティングとは、Web上における記事コンテンツを作成するのに適した書き方、または書くために必要なスキルのことです。紙媒体にライティングする場合とは異なる部分が多く、WebコンテンツにはWebライティングのテクニックを活用して作成する必要があります。
なぜWebライティングの書き方で書く必要があるのか?
Web媒体での書き方と紙媒体での書き方を分ける理由は、各媒体におけるユーザーの目的や行動が異なるからです。
- Web媒体でのユーザーの目的や行動
- 紙媒体でのユーザーの目的や行動
Web媒体でのユーザー目的や行動
まずWebサイトにおけるユーザーの心理として「目的の情報だけをすぐ取得したい」と思っています。例えばユーザーがある記事に辿り着いたとき、その記事にアクセスした理由としてよくあるのが、Webサイトを回遊しているときにたまたま気になった見出しがあったのでアクセスしてみた、という場合です。
つまり最初からしっかり見ようと思ってアクセスしたわけではなく、どのような結論であるかを知りたいと思ってアクセスしたのです。ユーザーはこういった状態のときに「知りたい情報がすぐ欲しい」と思っています。
そのため結論以外の文章を延々と読まされていると、しびれを切らして途中で離脱してしまう可能性が高くなるのです。そのためまずは結論から先に伝え、あとの文章はユーザーが読みたいと思ったら読ませるようにします。
紙媒体でのユーザーの目的や行動
一方で新聞や雑誌などの紙媒体は、ユーザーはじっくり読みたいと思って入手します。特に購入した本などはしっかり読むためにわざわざ時間をとって、最初から最後まで読もうとします。
このような場合は起承転結により、結論は先出しせず最後まで残しておくほうがユーザーは楽しめます。Web媒体と紙媒体はこういったユーザーの目的や行動が異なるため、それぞれの媒体に適したテクニックで書く必要があるのです。
Webライティングの書き方(手順)
Webライティングでは主に以下の手順で書き進めていきます。
- タイトル(H1)を付ける
- アウトラインを作成する
- リード文を作成する
- 本文を作成する
- 手直しや推敲を行う
タイトル(H1)を付ける
タイトルは見出しのH1に該当する部分です。ユーザーはタイトルを見てその記事を読むか否かを判断するため、最初の入り口として非常に重要なポジションとなります。メインキーワードを必ず左端に配置し、ユーザーの興味関心を引くタイトルを付けます。
およそGoogleの検索結果には30文字程度までが表示されます。超過分の文字は「…」で置き換えられてしまうため、検索クエリとマッチしなくなるので注意が必要です。
アウトラインを作成する
アウトラインは「輪郭、外郭」といった意味で、そのWebページの骨組みや構成のことを指します。アウトラインは見出しを組み立てていくことで作成できます。
一般的に大見出しはその内容の大枠を伝える見出しでHTMLでは「H2」となります。大見出し「H2」の内容を更に細分化したいときには中見出し「H3」を使用します。
そしてH3の内容を更に細分化する場合は、小見出しの「H4」を使用します。その下には「H5」もありますが、構成的にも細かくなりすぎてしまうため、一般的にはH4までがよく使用されます。
リード文を作成する
リード文はページの本文が始まる前の前置きとして、ユーザーを本文に導く役割があります。「リード=lead」とは「先導する」と言う意味になり、ユーザーを本文に先導できるか否かがこのポジションの重要な役割となります。
タイトル同様に、リード文はユーザーが本文をそのまま読み進めるか否かの判断を行う重要なフェーズです。ユーザーの興味関心を引き、本文を読みたいと思わせるような内容にしなければ、ユーザーは本文を読む前に離脱してしまいます。
ポイントとしては、ユーザーの悩みを提示し共感することで興味関心を引き、本文を読むまでユーザーは知ることができない事実をほのめかすことで、本文へ誘導できる可能性を高められます。
リード文を簡単に作成するには
リード文を簡単に作成するには以下のような順番で作成していくと、簡単に作成ができます。
- 共感 「~だと思いませんか?」「~ではありませんか?」「~ですよね?」
- 転換 「~は分かりませんでした」「本当は~ではありませんでした」
- 事例 「でも実は~だったのです」「実際には~でした」
- 結論 「当記事において~の真相を解説します」「当記事では~について説明します」
一つのフレームワークとして覚えておくとリード文の作成以外においても応用がききます。
本文を作成する
Web媒体における文章の作成方法は紙媒体とは違うことを上項目「なぜWebライティングの書き方で書く必要があるのか?」で解説いたしました。
Web上で公開する記事コンテンツの基本は「結論ファースト」です。つまり結論を先出ししたあとに、その結論についての理由を述べていきます。
こういった紙媒体には適用されないWeb独特のライティングは「PREP法」「SDS法」というフレームワークを活用して書いていきます。
PREP法とは
PREP法とはWeb上で公開する記事コンテンツを作成するときに用いられるフレームワークです。書き方としては「P」→「R」→「E」→「P」の順に書いていきます。
- Point(結論):まず結論を伝える
- Reason(理由):結論に対する理由を述べその根拠を伝える
- Example(具体例):具体的な事例を交えて更に詳細に解説する
- Point(結論):最後にもう一度結論を述べる
情報を分かりやすく論理立てて伝える方法として、ビジネスではよく使われるフレームワークです。
SDS法
SDS法もWeb上における記事コンテンツの書き方として広く浸透していますが、記事コンテンツだけにとどまらず、ある内容を端的に素早く伝えたい場合にもよく使われるフレームワークです。
- Summary(要点):まず要点を伝える
- Detail(詳細):要点に対して詳細に解説をする
- Summary(要点):最後にまとめとしてもう一度要点を伝える
SDS法は主にプレゼンテーションやスピーチなど、限られた時間内に分かりやすく内容を伝える方法としてよく使われるフレームワークです。またニュースなどの原稿を作成する際にもよく活用されます。
手直しや推敲を行う
コンテンツ記事を書き終えたらそのまま公開するのではなく、今一度漢字の間違いはないか、文章に違和感はないか、不自然な表現はないかを再度確認します。そのように再度手直しを行い何回も文章を推敲していくことで、完成度の高いコンテンツ記事に仕上げられます。
企業であれば「校正」や「校閲」が担当するフェーズですが、Webライティング能力を少しでも高めるために、自分でまずは何度も推敲してみることをおすすめします。
Webライティングの書き方(ターゲット設定)
個人ブログであれば自分の好きなジャンルを選び、好きなタイトルを付け、好きなように自分の書きたいことを書きます。ですがビジネス目的で運用するオウンドメディアなどでは、そのように書いていくわけにはいきません。
狙ったキーワードで上位表示させ、Webサイトから「CV=コンバージョン」を発生させるという目的があるからです。そのためには本文を書き始める前に、まず以下の項目をしっかりと設定しておく必要があります。
- ペルソナを設定する
- CV発生までの筋道を立てる
- 競合サイトを確認する
ペルソナを設定する
ペルソナとは記事コンテンツを発信しようとする「相手=ユーザー像」のことを指します。自分の書いた記事コンテンツを「誰に」向けて発信していくのか、具体的なユーザー像を設定します。ユーザー像は架空の人物となりますが、実際に存在している人物をモデルに設定するのがペルソナの重要なポイントとなります。
注意点として、自分の都合の良い人物像を設定しないようにすることです。あくまで市場調査により統計やデータから導き出された人物像をペルソナにする必要があります。
ペルソナはユーザーの悩みや疑問から設定する
ペルソナはユーザーの悩みや疑問から設定をします。ユーザーは悩みや疑問を解消するべくWebサイトに訪れます。CVが発生するときというのは、当該Webサイトの商品やサービスが自分の悩みや疑問を解消してくれるとユーザーが判断したときです。そのためにはまず4つのクエリからユーザーがどのクエリに属しているのかを判断します。
4つのクエリとは?
まずクエリとは「問い合わせる」「質問する」などの意味となり、いわゆるユーザーが検索エンジンを通して検索した語句のことを指します。そしてユーザーは以下の4つのクエリのいずれかに属しています。
- Knowクエリ:知りたい
- Buyクエリ:買いたい
- Goクエリ:行きたい
- Doクエリ:したい
ユーザーはこの4つのクエリのうち、どのクエリに属しているのかを知ることで記事コンテンツにもメリハリをつけることができます。
例えばGoクエリに属しているユーザーであれば、Googleマップを記事コンテンツ中に入れる、スポット情報を多めに紹介する、駐車場情報などを盛り込む、など地域情報を強化することでユーザーの満足度を高められます。
CV発生までの筋道を立てる
Webサイトの目的はそのサイトからCVを発生させることです。つまり「商品を購入させる」「資料を請求させる」「予約を取らせる」など、そのWebサイトには何らかの目的があって運営されています。こういった役割がある以上、CV発生までの筋道を立てておく必要があります。
どのようなキーワードでユーザーをWebサイトに流入させ、どういった記事を読ませて興味関心を高め、そしてCVに繋がらせるのか、ユーザーを辿らせる経路を逆算をして具体的な筋道をイメージしておきます。
競合サイトを確認する
狙っているキーワードですでに上位表示されているWebサイトの確認を行います。すでに上位表示を達成しているWebサイトは、Googleなどの検索エンジンが優良Webサイトと判断しているから上位に表示されています。
インターネット黎明期において、小手先のSEOテクニックが通用していたときもありましたが、現在ではそういった類はほぼ通用しないようになっています。
本当にユーザーにとって有益といえるWebサイトしか上位表示されていないと判断できますので、そういった優良Webサイトをお手本にします。
どういった構成をしているのか、どのような内容が書かれているのか、どのくらいのボリュームなのかを確認し、自分のWebサイトにも取り入れていきます。競合サイトはなぜ上位表示できているのか、といった視点を常に持つようにします。
Webライティングの書き方(本文)
Webライティングと聞くと検索エンジン(クローラー)に好かれることだけを考えて記事コンテンツを書いてしまいます。
しかし文章を読むのは人間であり、しっかり人間に読まれる記事コンテンツを書くことが検索エンジン上位表示への近道となります。
しっかりユーザーに読まれるためには「正しい日本語」「きれいな文章」を意識した「人間が読んでいておかしくない言葉遣い」で文章を書く必要があります。
以下の項目を意識して記事コンテンツを書くことで、非常にきれいな文章に仕上げることができます。
- 長文はいくつかの短文に分ける
- 箇条書き(リスト表示)を活用する
- 一文一義を意識する
- 冗長表現に気をつける
- 同じ語尾は2回以上連続でくりかえさない
- 接続詞・接続助詞・格助詞を控えめに
- 「たり」は2回使う!「たりたり」の法則
- 主語と述語はなるべく近くに置く
- 文章のねじれに気をつける
- 形容詞は修飾する名詞の直前におく
- 副詞は修飾する語句の直前におく
- 指示語はNG
- 否定文ではなくなるべく肯定文にする
- 重複表現(重ね言葉)を避ける
- 二重敬語は逆効果
- 二重否定は冗長表現と受け取られがち
- 大げさな表現は簡単にする
- 表記ゆれに注意
- 同音異義語の変換ミス
- 口語ではなく文語を使用する
- 「い」抜き言葉や「ら」抜き言葉に注意する
- 意味があまり変化しない語句は極力省く
- 主観的記事はWebサイトの方向性に注意
- 文章にもリズムがある
- 文章にアクセントを付ける「体言止め」
長文はいくつかの短文に分ける
文章の書き始めから一文の終わりである句点「。」までが長すぎると、主語と述語が離れ何を伝えたい文章なのかが分かりづらくなります。そのため長文はいくつかの短文に分けるようにします。
明確な定義はありませんが、おおよそ60文字~80文字程度が一文の長さとしては最適と言われています。一文で120文字を超えるようであれば、どこかで文章を区切れないか検討するのがおすすめです。
箇条書き(リスト表示)を活用する
単語や項目が複数ある場合などは、箇条書きを活用するとすっきり見やすく表記ができます。例えば「リンゴ」「ミカン」「バナナ」「イチゴ」「パイナップル」などと続けて横書きにするのではなく、下記のように箇条書きにします。
- リンゴ
- ミカン
- バナナ
- イチゴ
- パイナップル
一文一義を意識する
ユーザーにもっとも伝わりやすいシンプルな執筆方法は「一文一義」で書くことです。一文一義は文章一文に対してひとつの事柄を伝えます。よけいな情報が他に入らないためとてもユーザーに伝わりやすくなります。
冗長表現に気をつける
冗長表現とは「本題と無関係な話題や表現」のことです。文字数稼ぎとも思える不要な言葉や、まわりくどい言いまわしが文章中多く含まれ、ダラダラと無駄に長い文章となります。ユーザーに対して伝えたいことが伝わりづらくなり、非常に稚拙な印象を受ける文面となりがちです。
同じ語尾は2回以上連続でくりかえさない
「です」「ます」などの語尾に使用される語句は、連続で重ならないようにします。明確な基準はありませんが、1つのパラグラフ(文章の段落)内に同じ語尾を2回以上連続で入れないように意識すると違和感が減少します。
- ❌例:今日は友人の家で誕生日会です。友人は今日で20歳です。この日のために予約しておいたケータリング・オードブルが楽しみです。
- ◯修正例:今日は友人の家で誕生日会です。友人は今日で20歳になります。この日のために予約しておいたケータリング・オードブルが楽しみです。
接続詞・接続助詞・格助詞を控えめに
接続詞・接続助詞・格助詞はそれぞれ個別の文章をつなげたり、他の語句との関係性を示せたりするとても便利な品詞です。しかし多用しすぎると読んだときに違和感を覚え、稚拙な文面となることがあります。
接続詞を控えめに
接続詞は活用がない自立語です。それ単独で接続語になります。
- 順接「それで・だから・したがって」など
- 逆説「しかし・ところが・けれども」など
- 累加・並立「それから・そして・および・また」など
- 説明・補足「なぜなら・つまり・ただし・もっとも」など
- 対比・選択「あるいは・それとも・もしくは・または」など
- 転換「ところで・さて・では」など
接続助詞を控えめに
接続詞が自立語なのに対し、接続助詞は自立語ではありません。それ単体では意味をなさない語句となり、主に前後の文の関係を示します。
- 「と」「が」「ば」「し」「て(で)」「のに」「ので」「から」「ても(でも)」「けれど(けれども)」など
格助詞を控えめに
格助詞は体言(名詞)に付いて、他の語句との関係を示します。
- 「に」「の」「と」「が」「へ」「で」「を」「より」「から」など
「たり」は2回使う!「たりたり」の法則
「たり」は並立助詞(並列助詞)に分類され、前の文章と後ろの文章が対等な関係の時、これらを列挙するために使う言葉です。主に具体例が2つ以上ある時に使用します。
この他にも「に」「の」「や」「と」「か」「なり」「だの」「やら」などがあります。
- ❌例:休日はインターネットをしたり、テレビを見て過ごします。
- ◯修正例:休日はインターネットをしたり、テレビを見たりして過ごします。
「たり」が1回使用でも問題ない場合
具体例が1つしかない場合は「たり」が1回の使用でも 文法上誤用にはあたりません 。ですが、間違いと受け取られることもありますので、なるべく2回使用を原則とした方がよいでしょう。
- ◯例:休日はインターネットをしたりして過ごします。
「たり」を3回以上使用する場合
「たり」は3回以上連続で使用しても文法上誤用にはあたりません。ですが文章が稚拙になったり、冗長表現になったりしますので、あまり多用はおすすめできません。
- ◯例:休日はインターネットをしたり、テレビを見たり、本を読んだりして過ごします。
主語と述語はなるべく近くに置く
主語と述語が近ければ文章はそれだけシンプルになり、意味が伝わりやすくなります。意味が伝わりづらい文章の特徴として、主語と述語が離れすぎていることが挙げられます。
主語と述語が離れれば離れるほど、その間にはよけいな語句や情報が多く入りますので、ユーザーが混乱する原因にもなります。
文章のねじれに気をつける
「文章がねじれている」という表現があります。これは主語と述語の関係性が崩れているときによく言われます。
- ❌例:私の目的は寄付金を集め、できるだけ多くの難民を救えればいいなあと思います。
→「私の目的」が「思います」となって主語と述語の関係性が崩れています。
- ◯修正例:私の目的は寄付金を集めること。できるだけ多くの難民を救えればいいなあと思います。
→「私の目的」が「寄付金を集めること」となり、シンプルに分かりやすく意味が伝わってきます。
形容詞は修飾する名詞の直前におく
例えば「大きい」「かわいい」など、ものの状態を表す語句が形容詞ですが、この形容詞は修飾する名詞の直前に置くのが基本です。形容詞とそれを修飾する名詞が離れれば離れるほど、その形容詞がどの名詞を修飾しているのかが分かりづらくなっていきます。
- ❌例:この大きい私の飼っているかわいい目をしたラブラドール・レトリーバーを見てください!
→大きいのが「私」なのか「かわいい目」なのか「ラブラドール・レトリーバー」なのかが分かりづらくなっています。
- ◯修正例:私の飼っているかわいい目をしたこの大きいラブラドール・レトリーバーを見てください!
→大きいのが「ラブラドール・レトリーバー」であることが分かります。
副詞は修飾する語句の直前におく
例えば「とても大きい」の「とても」が副詞ですが、この副詞は修飾する語句の直前に置くのが基本です。副詞とそれを修飾する語句が離れれば離れるほど、その副詞がどの語句を修飾しているのかが分かりづらくなっていきます。また付帯する場所によっても意味合いが変わってきます。
- ◯例:私の飼っているとてもかわいい目をしたこの大きいラブラドール・レトリーバーを見てください!
✅かわいい目を強調している
- ◯例:私の飼っているかわいい目をしたこのとても大きいラブラドール・レトリーバーを見てください!
✅ラブラドール・レトリーバーの大きさを強調している
- ❌例:とても試験を受けるのに緊張している
✅副詞が離れ過ぎている
◯修正例:試験を受けるのにとても緊張している
■他にも以下のような例があります。
- きらきら光る:形容詞を修飾
- ふらふら歩く:動詞を修飾
- 大した男だ:名詞を修飾
指示語はNG
指示語とはいわゆる「こそあど言葉」のことです。こそあど言葉とは「これ」や「それ」「あれ」や「どれ」のような「ある物事」を指し示す言葉です。これら4語の頭を取って「こそあど」と呼ばれています。
指示語を多用すると、ユーザーは何について書かれている文章なのかが分かりづらくなっていきます。書いている本人は内容を把握していますが、ユーザーは把握できていない場合もあります。そのため指示語は極力使用しないようにしましょう。
否定文ではなくなるべく肯定文にする
Webライティングでは否定文で表現するよりも、なるべく肯定文で表現する方が好ましいとされています。それは肯定文の方が文章を明確に、そして簡潔に表現できることが多いからです。しかしながら文脈によっては、否定文を採用する方がしっくりくる場合もあります。
- ❌例:電気がつけっぱなしでないことを確認してください
- ◯修正例:電気を消したか確認してください
重複表現(重ね言葉)を避ける
重複表現は重ね言葉とも言われ、同じ意味の言葉が重複して使われていることを指します。
例として以下のようなものが挙げられます。
- ❌一番最初に→◯一番に、◯最初に
- ❌一番ベストです→◯一番です、◯ベストです
- ❌まずはじめに→◯まず、◯はじめに
- ❌馬から落馬する→◯馬から落ちる、◯落馬する
- ❌再び再選する→◯再び当選する、◯再選する
二重敬語は逆効果
Webライティングでは過度な敬語も冗長表現と受け取られることがあります。例えば以下は二重敬語として、まわりくどい表現と捉えられがちです。
- ❌~させていただきます→◯~いたします
✅「させて」と「いただく」で二重敬語となっています。
- ❌行わせていただきます→◯行います
✅「行わせて」と「いただく」で二重敬語となっています。
- ❌おっしゃられる→◯おっしゃる
✅「おっしゃる」と「られる」で二重敬語となっています。
- ❌お越しになられますか→◯お越しになりますか
✅「お」と「なられる」で二重敬語となっています。
二重否定は冗長表現と受け取られがち
二重否定は文章にアクセントを付ける意味合いで意図的に使用されることもありますが、多くの場合は冗長表現と受け取られがちです。二重否定はできる限り肯定文にすることですっきりとした文章にできます。
- ❌例:あなたもこの方法に従ってやっていけばできなくもないでしょう
✅「できなくも」と「ない」で二重否定となっています。 - ◯修正例:あなたもこの方法に従ってやっていけばできる可能性はあります
- ◯修正例:あなたもこの方法に従ってやっていけばできるかも知れません
- ❌例:弱点を攻めれば勝てないわけではありません
✅「勝てない」と「ありません」で二重否定となっています。 - ◯修正例:弱点を攻めれば勝てる可能性はあります
- ◯修正例:弱点を攻めれば勝てるかも知れません
いずれの場合も否定文ではなく肯定文にすることで、よりシンプルになっています。
大げさな表現は簡単にする
小説などにおいて、意図的に表現を難しくして文面にアクセントをつけることもありますが、多くの場合は冗長表現と受け取られがちです。
- ❌例:この商品は売り出せば大ヒットする可能性を秘めているものである
- ◯修正例:この商品は売り出せば大ヒットする可能性がある
- ◯修正例:この商品は売り出せば大ヒットするかも知れない
表記ゆれに注意
文章中にひとつの意味を表す語句に対して、複数表記されていることを表記ゆれと言います。文面が統一されずいびつな感じになり、ユーザーが意味を取り違える可能性もあります。
例
- 「犬」「いぬ」「イヌ」「戌」
- 「ベッド」「ベット」
- 「メモリ」「メモリー」
- 「PC」「パソコン」
- 「HDD」「ハードディスク」
- 「スマホ」「スマートフォン」
- 「アプリ」「アプリケーション」
- 「行う」「行なう」
など
同音異義語の変換ミス
読み方や発音は一緒で、意味が異なる語句を同音異義語と言います。これら同音異義語の変換ミスにも注意しましょう。
例
- 「意思」と「意志」
- 「異動」と「異同」
- 「以降」と「移行」
など
口語ではなく文語を使用する
文章を書く際には口語ではなく文語を使用します。口語は「話し言葉」文語は「書き言葉」です。ただし例外として小説やエッセイ、個人ブログなど一部口語調でもよいケースはあります。
- ❌いろんな:◯いろいろな
- ❌すいません:◯すみません
- ❌やる:◯行う
- ❌どんどん:◯急速に
- ❌やっぱり:◯やはり
- ❌いっぱい:◯多く
- ❌ちょっと:◯少し
- ❌ちゃんと:◯きちんと ◯しっかり
- ❌すごい:◯非常に ◯大変
- ❌~じゃない:◯~ではない
- ❌~しちゃう:◯~してしまう ◯~行ってしまう
など
「い」抜き言葉や「ら」抜き言葉に注意する
ある表現に対して「い」や「ら」が抜けていることを「い」抜き言葉「ら」抜き言葉といいます。会話ではあまり気になりませんが、文章の場合はNGとされています。特に企業Webサイトやビジネス文章などでは抜け落ちに気をつけましょう。
例
- ❌食べれる:◯食べられる
- ❌食べてる:◯食べている
- ❌来れる:◯来られる
- ❌来てる:◯来ている
など
意味があまり変化しない語句は極力省く
書いても書かなくてもたいして意味が変化しないような語句は、冗長表現にならないためにも極力省きます。ただし文章に含みを持たせたり、アクセントをつけたりする意味合いで、意図的に使用する場合もあります。
- ❌例:夜は基本的に12時に就寝します
✅「基本的に」は、なくても意味は通じるので省きます。 - ◯修正例:夜は12時に就寝します
- ❌例:ある意味わたくしは
✅「ある意味」は冗長的になるので省きます。 - ◯修正例:わたくしは
- ❌例:~ということです
✅「ということ」は冗長的になるので省きます。 - ◯修正例:~です
- ❌例:~することができます
✅「する」と「できる」で二重に同じ意味が重なっていますのでひとつにします。ただし文脈によっては「することができます」の方がしっくりくる場合もあるので、あまり多用はせずケースバイケースで使い分けましょう。 - ◯修正例:~できます
- ❌例:そのようにして、彼はチャンピオンに上り詰めました
- ❌例:このように、彼はチャンピオンに上り詰めました
✅前の文脈からの流れも加味する必要はありますが「そのようにして」や「このように」も、なくても意味が通じる場合が多いためできるだけ省きます。
主観的記事はWebサイトの方向性に注意
記事を書く際にはその記事の内容を「客観的」にするのか「主観的」にするのか、内容の方向性を統一する必要があります。
■客観的とは
特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま
引用:weblio (https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%A2%E8%A6%B3%E7%9A%84)
客観的記事とは、第三者目線で執筆されている記事になります。自分の立場からものごとを判断するのではなく、根拠のあるデータや資料などに基づいて述べられており信頼性と説得力があります。
■主観的とは
自分ひとりのものの見方・感じ方によっているさま
引用:weblio (https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%BB%E8%A6%B3%E7%9A%84)
一方で主観的記事とは、個人の意見や主張、見解で書かれている記事のことです。根拠がなかったり、客観的データに乏しかったりすることも多く、独り善がりな記事になりがちです。ユーザーから「あなたがそう思っているだけでしょ」と思われてしまうこともあります。
個人ブログやレビューサイトであれば問題はありませんが、企業が運営するWebサイトやビジネス関連ブログにおいてはあまりおすすめできません。
文章にもリズムがある
読んでいて読みやすいと感じる文章に出会うこともあります。そのような記事はテンポよく読み進められるものです。
一方で読んでいてなんとなく違和感があったり、歯切れが悪かったりする記事もあります。このような場合は冗長表現が多く入り、文章にぜい肉が付いている可能性があります。
人それぞれ感じかたは違いますが、やはりリズミカルな流れを意識して書かれている文章は読みやすいと感じるものです。テンポがよくリズミカルな文章にするためには文章にアクセントを付けるのがおすすめです。
文章にアクセントを付ける「体言止め」
「体言止め」は文章に詩的な感じを加えるためによく用いられるテクニックです。動詞で終わるところをあえて体言(名詞)で終わらせるようにします。古くは俳句や和歌などで、余韻や余情をもたせるために使用されていた技法です。
例
- 明日は待ちに待った誕生日です
→✅明日は待ちに待った誕生日
- なんて素晴らしい青空でしょう
→✅なんて素晴らしい青空
など
非常にリズミカルな感じを醸し出せるテクニックです。ですがあまり多用しすぎると文章が稚拙な感じになりますので、使いどころを考慮する必要があります。
Webライティングの書き方とは?SEO Webライターが解説!コンテンツ ライティングの基本 まとめ
Web上で公開する記事コンテンツはWebライティングで書く必要があります。しっかりとペルソナでユーザー像を設定してから、CV発生までの経路を逆算して記事コンテンツを作成していきます。
そして記事コンテンツを読むのは人間であることを意識しながら、違和感のないきれいな日本語で文章を書いていきましょう。
SEO Webライター佐藤がSEO記事の作成をいたします!
SEO Webライター佐藤がSEO記事を作成いたします。